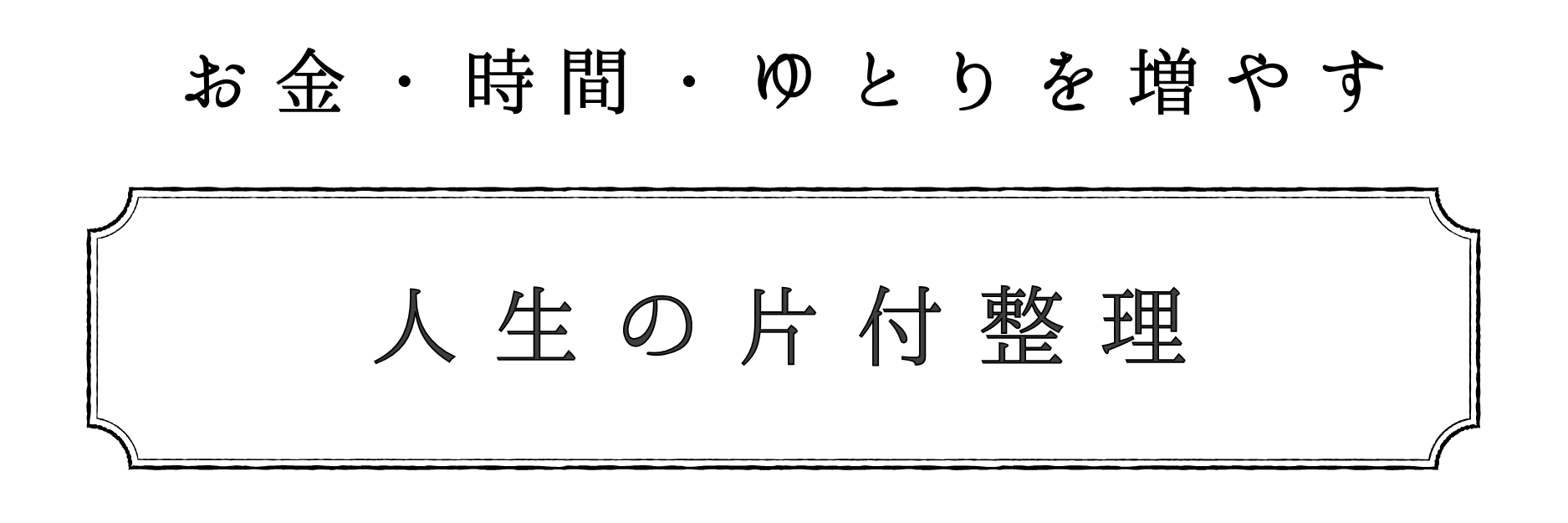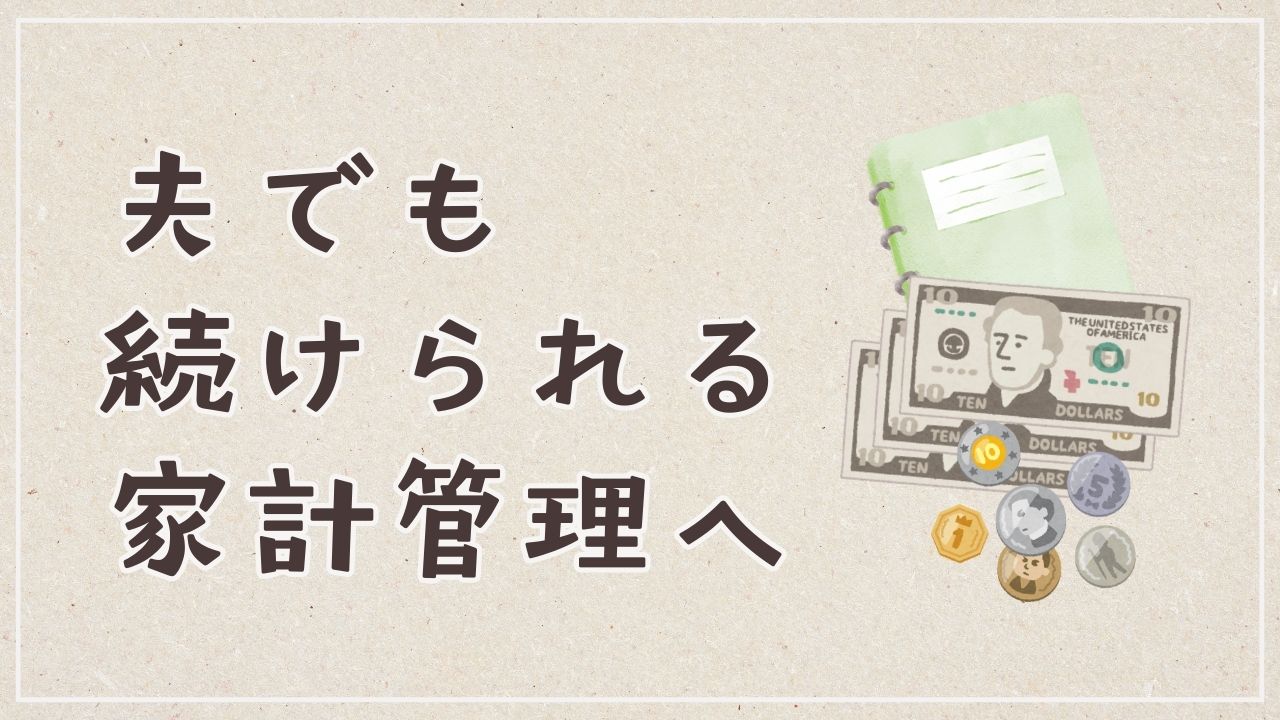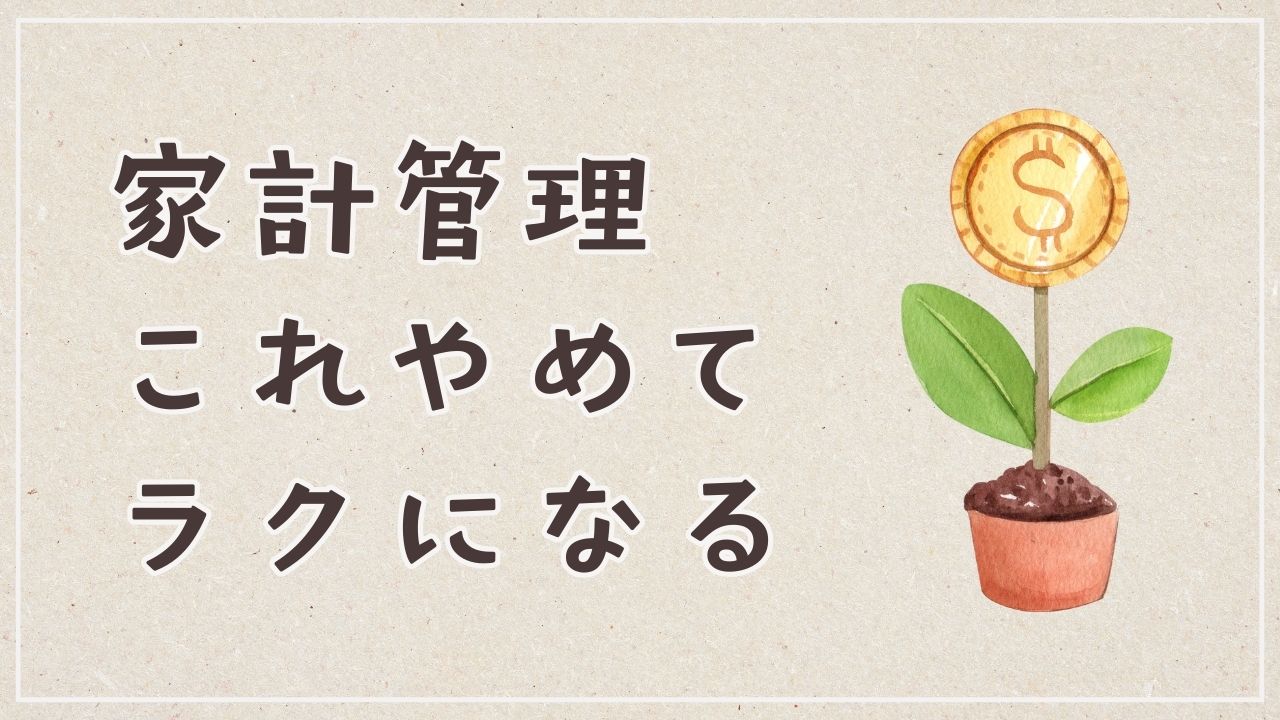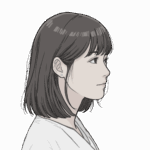
片付整理アドバイザーのオリです!お金・時間・心のゆとりを増やす「片付整理」を発信しています。
私の夫は、結婚前から家計管理が苦手です。そして私も、家計管理は得意な方ではありません。
ある仕事休みの週末、たまったレシートを日付順にまとめ、自作のパソコン家計簿に入力していました。

はぁ、もう嫌…面倒くさっ…
その時にふと感じました。

この面倒な家計管理、夫はできるんだろうか?
なぜなら、夫はパソコンが苦手だからです。
だから、パソコン家計管理は絶対にやりたくないだろうし、むしろできないと思いました。
「私がもし明日いなくなったら…」

…
ちょっと考えただけで、ぞっとしました。
夫は、我が家の家計管理のことは深く知りません。というか、話をきちんと聞いていません。
しかも、口頭で共有しているだけなので、お金の管理は絶対に「任せられない」と感じたわけです。

今の家計管理を根本的に見直さないと…
そう思い、私が今すぐ取り組むべきなのが、お金の片付整理でした。
そして、お金の管理方法を、
私ができる家計管理ではなく、誰でも(夫でも)続けられる家計管理に変える必要がありました。
誰でも続く家計管理とは?

まず、誰でも続く家計管理って、どんな家計管理なんだろう?と考えました。
おそらく、誰もがこう答えると思います。
「簡単、手間なし、楽しく続けられる家計管理」(なんだか料理のようですね)
「簡単」というのは、言い換えると「難しくない」ということです、
パソコンやスマホで管理するデジタル家計簿は、パソコンが苦手な夫には難しい管理方法です。
「手間なし」というのは、家計管理に時間がかからないことです。
「楽しく続けられる!」というのは、これは間違いなく黒字家計の状態です。
誰だって、難しくて複雑な家計管理は嫌だろうし、そもそも赤字家計の管理も楽しくありませんよね。
だから私は、我が家の家計管理を見直すことにしました。
それは、「夫でもできる、簡単、手間なし、楽しく続けられる家計管理」です。
夫が無理なくできる家計管理の方法を知る
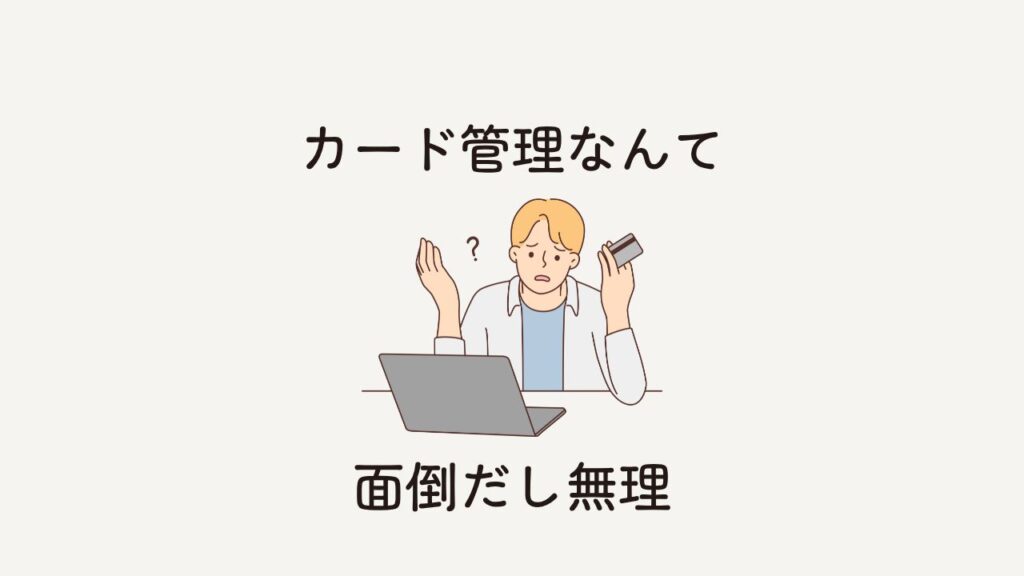
まず夫は、ニコニコ現金払いが好きです。
なぜなら、クレジットカード払いの管理は「面倒だし、自分には絶対にできない」と分かっているからです。
クレジットカード払いはポイントが貯まるメリットはありますが、管理が複雑で赤字家計のきっかけにもなります。
私も過去ポイント欲しさに、ほぼ全ての支払をカード払いにしていた時期がありました。
そして、翌月のカード明細書を見てかなり焦った経験があります。
私も忘れがちですが、クレジットカード払いは「借金」です。
現金で払えるけど、ポイントが欲しいから、変わりにクレジットカードを使う。
そして、カード払いの後は、その金額をカード払い用の口座に振り分けておく。
これをしないから、翌月の明細書を見て焦るんですね。
日々、家計管理と向き合ってる私でも、クレジットカード払いの管理は複雑で面倒だと思っています。
だからこそ、私の夫が無理なく続けられる家計管理は、現金がベースの家計管理となります。
家計簿は細かく書かない家計管理を目指す
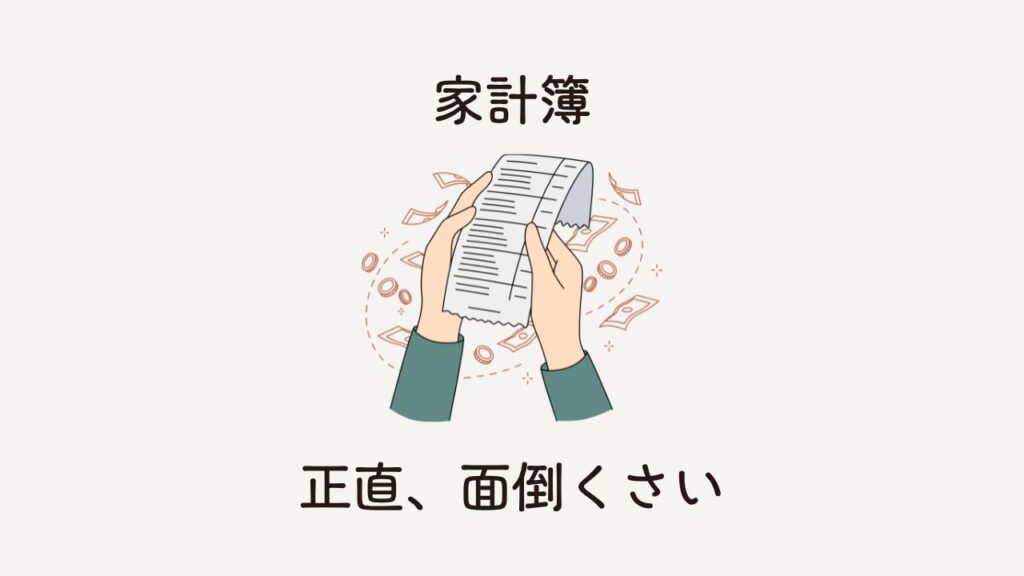
私がこれまで試した家計簿は、市販の家計簿ノートからスマホのアプリまで色々あります。
結局どれも長く続かず、たまったレシートを見て、家計簿を書くことを後回しにしていたんです。
それでも、赤字家計から脱出したくて、仕事が休みの週末に嫌々家計簿を書いていたんです。
自分では「ぬけ、もれ」なく支出金額を書いていたつもりですが、赤字が黒字になることはありませんでした。
もし家計簿を書かなくてもいいなら、正直、面倒なので書きたくないのが本音です。
でも家計簿は必要だと思い、もう一度考えました。

私は何の目的で家計簿に記録しているのか?
その答えは、家計簿を書いて貯金をすることが目的です。
それがいつの間にか、ただ支出を記録しているだけの家計簿になっていたんです。
本当は、家計簿を毎日書かなくても、「予算を守りマイナスにならない仕組み」ができていればいいわけです。
そしてその「予算を守る家計管理」を現金管理にしたら、私の夫でも家計管理を共有できるようになりました。
まとめ|夫が続けられる家計管理へ
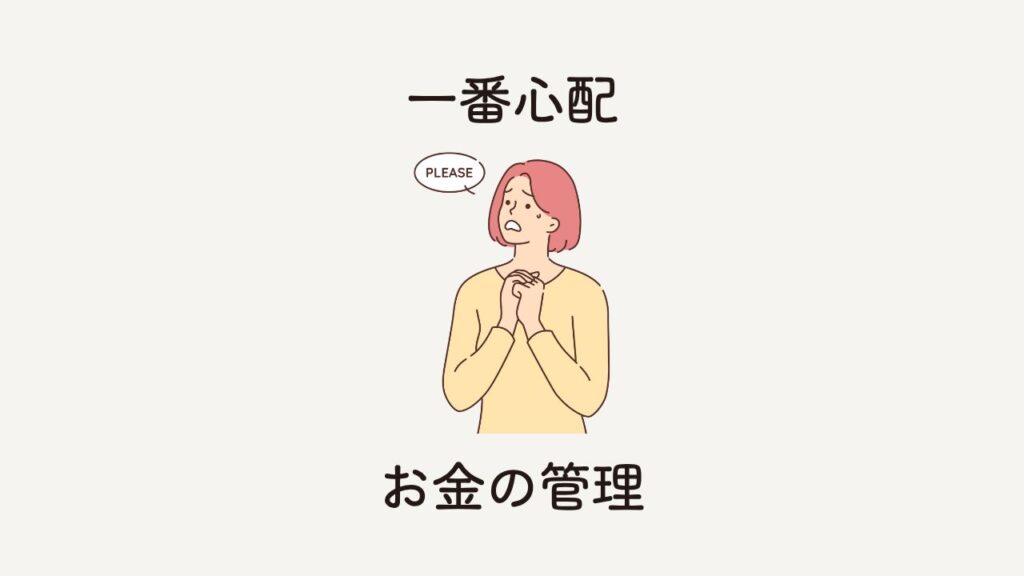
私も40代に入り、自分自身の健康や親の終活が気になるようになりました。
我が家には3人の子供たちがいますが、私がもし、明日この世を去ったら…。
そう考えると、一番心配なのはお金の管理です。
夫や子供たちの生活、学校の費用など、私が居なくなっても家計管理は続きます。
だからこそ、夫や子供たちが困らないようにするために、私は生前整理をはじめました。
そして、私の代わりに家計管理を引き継ぐ夫は、私の家計管理は通用しません。
私ができる家計管理ではなく、夫でも続けられる家計管理へ見直して、普段から共有することにしました。